大規模都市開発が集中する東京の都心部で、各エリアが個性的な魅力を分担し、全体で多様さを誇るような都市づくりはなされてこなかったのではないか。東京圏が活力を持ち、国内経済の推進力、そして日本の国際競争力の要となるために今のままでよいのか。
例えば、都市開発の担い手である大手デベロッパーの間で、競争しつつ共創できる環境があれば、より合理的に東京の価値を上げる道があるのではないか──。
近年の都市開発、特に大手デベロッパーが携わる都心部のエリア構築に対し、パノラマティクス主宰の齋藤精一氏は上記のような問題提起をしている。その問い掛けに応じた大手デベロッパー複数の担当者などとの間で、2019年から定期的に議論の場「202X URBAN VISIONARY」が持たれてきた。
以下では、そのうちエリアマネジメントの活動やデジタル技術に備わる「横断力」をどう生かせるかという観点から、各参加者の見解を整理してみたい。本レポートは主に、2020年10月に、MIYASHITA PARK内にある三井不動産ホテルマネジメント社の運営する『sequence MIYASHITA PARK』からYou Tubeでライブ配信された、第5回のトークセッションをベースに構成している。
【第5回登壇者】
齋藤精一(ライゾマティクス・アーキテクチャー主宰)【司会進行】
豊田啓介(noiz 共同主宰/gluon 共同主宰)
山本恵久(日経クロステック/日経アーキテクチュア 編集委員)
田中陽明(春蒔プロジェクト株式会社 代表取締役/co-lab企画運営代表)
雨宮克也(三井不動産株式会社 開発企画部 開発企画グループ長)
鈴木将敬 (三菱地所株式会社 コマーシャル不動産戦略企画部 副主事)
杉山央(森ビル株式会社 タウンマネジメント事業室 新領域企画部 課長)
山口堪太郎(東急株式会社 経営企画室 経営政策グループ 課長)
(1)齋藤氏の設問──東京全体を俯瞰する戦略はあるか?

不動産デベロッパーは長い間、スクラップ&ビルドによって不動産の価値を上げ、売却あるいは賃貸による収入を得るビジネスを基幹としてきた。用途ミックスなどによる価値創造(都市貢献)と引き換えに、再開発の際に容積率の割り増しを受けるなどハードのボリュームを追求してきた経緯がある。
都心部では、つくる段階から当面は使う段階に移行する拠点も多い。近年は、ハード開発にとどまらず、サービス開発を強化するデベロッパーの動きが目立つ。大手各社はそれぞれの旗艦地区でエリアマネジメント領域に乗り出し、「サービサー」としてエリア経済を主導する役割を担おうとしている。
といっても、エリアの構築は別個に進み、東京全体を俯瞰する戦略が取られていないきらいがある。東京都が、全体像を導いているようにも見えない。その中で「サービサーとしてのデベロッパーは今後、どんなドメイン(依拠する領域)をつくらないといけないのか?」。齋藤氏は改めてそう問い掛ける。
そもそも、大手デベロッパーの携わる都心部のエリアマネジメントの現場には、今、どのような変化が起こっているのか。
エリアマネジメント組織の先駆「大丸有(大手町・丸の内・有楽町)エリアマネジメント協議会」は02年に発足し、20年近くの歴史がある。中核企業である三菱地所の開発推進部理事エリアマネジメント推進室長、藤井宏章氏によると、動きが一気に加速したのは2010年代の後半に入ってからだという。
- 三菱地所の藤井氏──「様々な規制緩和が進み、道路などを活用できる状況になったのが大きい。社会課題が細分化する中で、エネルギー管理やイノベーション創発などの仕組みづくりをビル単位ではなく街で進めたいという要請が生じた。そうしたソフト面で、エリアマネジメントに期待がかけられている」
三菱地所は20年1月に「丸の内NEXTステージ」 の始動を発表。丸の内再構築の第3ステージと位置付け、イノベーション創発とデジタル碁盤強化をうたう。三菱地所エリアマネジメント企画部専任部長の金城敦彦氏は、「オープン・イノベーション・フィールド」としての街の在り方を強調する。
- 三菱地所の金城氏──「街の魅力づくりをリードする企業を誘致するのが、デベロッパーの重要な仕事の1つだ。街を人々の交流の舞台と位置付け、先進企業による実験の場として使っていく。そのためには企業に、『この街で仕事をすれば良い成果を出せるのではないか』と評価してもらう必要がある」
一方、三井不動産は、04年のコレド日本橋開業を手始めに「日本橋再生計画」に着手した。19年のコレド室町テラスの開業以降を新たな時代(第3ステージ)と位置付ける。「グレーター日本橋」と呼ぶ広域のエリアを対象とし、現在はその一画を担う日本橋室町エリアマネジメントが街づくりを主導する。
三井不動産開発企画部開発企画グループ長の雨宮克也氏も、「エリアの価値を上げるために街を育てる方向に、エリアマネジメントが進化してきた」と語る。当初はエリアブランディングのためにテナントを囲い込む側面があったのは否めない。しかし、近年は、場を提供する役割にシフトしてきた。
- 三井不動産の雨宮氏──「場を設け、イノベーションに向けた自由な活動を見守る在り方に変わった。コロナ禍で改めてDXが重要な課題として浮上し、さらに変化するとみている。テナントが場に対するオーナーシップを発揮し、街への寄与や貢献を始める。互酬性やボーダレスがキーワードの時代になる」
このように各社が「開かれた場の提供」を掲げるのは、”大家”の側からトップダウンで仕掛けるよりも、個々のテナント企業や協力者によってエリアマネジメントが「自走する状態」を理想として描いているからだ。街を利用する人々の自発性に期待し、ボトムアップの力を引き出そうとしているわけだ。
ボトムアップ型でエリアの価値を高めるためには、「みんなで取り組みたくなるような共感型のテーマを街に対して設定する必要がある。以降、テナント企業などの間で自然と共創が起こるような流れが望まれる」と、三菱地所コマーシャル不動産戦略企画部副主事の鈴木将敬氏は強調している。
- 三菱地所の鈴木氏──「こちらから呼び掛ける従来型よりも、一人ひとりが街の楽しみ方や空間の使い方を自ら発見する在り方の方が理想的だ。コロナ禍でリモートワークが増えた結果、個々の身の回りをカスタマイズで改善しようとする人たちが増えた。そうした傾向と合致するものだと考えている」

春蒔プロジェクト代表の田中陽明氏は、街の活動に積極的にコミットする「セルフパフォーマー」の存在に目を向ける。同氏はこれまで、クリエーターによる自律的な協働の誘発を目的とするシェアオフィス「co-lab(コーラボ)」を展開してきた。同様の仕掛けを街にも広げていけるという考え方だ。
- 春蒔プロジェクトの田中氏──「官民が協力し、自主的に利用できる空間環境を賃料のかからないプラットフォームとして用意できれば、クリエーティブに街を使う活動の持続性を経済面から支援できる。一定の利用ルールを設ける必要はあるが、様々な魅力を街に生み出すために有効な手段となり得るはずだ」
ボトムアップ型に関しては、近年、「タクティカルアーバニズム」と呼ばれる取り組みが現れている。道路や公園、河川などパブリックスペースの活用の短期的な社会実験を重ねながら、その定着を図るものだ。
エリアににぎわいを生み出す、そうした活動の担い手は着実に増えてきた。可搬性のあるファニチャーやキッチンカー、タイニーハウス(小屋)など、機動力のある空間的な仕掛けを駆使しながら取り組んでいる。
瞬発力のある短期的な実験とは別に、より中長期の実験を前提とする「ラボ型」の有効性も明らかになってきた。企業間や官民の共創を図る趣旨で、小規模の拠点を街に埋め込む。トップダウンとボトムアップの間にある方法だ。03年に第1号(六本木)を開設した前述co-labは、その先駆的な存在となる。
田中氏は、新たな展開として福井駅前に建設中の再開発ビル内に開設予定の「リビングラボ」の可能性を説いている。森ビル都市企画がコンサルとなって進める「福井駅前電車通り北地区A街区再開発」(組合施行)と近隣の商店街を結び付け、地方都市の中心市街地活性化に役割を果たそうとしている。
- 春蒔プロジェクトの田中氏──「再開発全体のコンセプトにも協力し、イノベーションを担うリビングラボとしてco-labが入居する計画。商店街側にも展開し、駅前エリア全体を実験の対象とする仕組みをつくりたい。北陸3県の中で特徴に欠ける福井で、ラボ型で個性を打ち出してはどうかと提案している」
大丸有では三菱地所が、金融関係のコワーキング『FINOLAB(フィノラボ)』を16年に開設した。また、日本橋でライフサイエンス分野に注力する三井不動産は、ウェットラボの開設を支援している。模擬実験を旨とするドライ型と違って実際の装置を用いるので、多彩な人材が出入りして影響を与え合う機会が増える。
齋藤氏は、「都市に求められる業務機能が東京に偏って集中し過ぎず、しかし、各地にばらばらにもなり過ぎないために、こうした共創のためのラボの設置も戦略的に考える余地がある」と語る。「都市集中型と地方分散型のバランスが問われるアフターコロナの時代に、着地点を見いだす手法として活用できるはずだ」
都心のエリアが個性を分担し、東京全体の魅力と競争力を高める──。といった当初のテーマから、国内の各都市が個性を分担し、日本全体の魅力と競争力を高めるという視点に発展していった。しかし、いずれにしても社会や技術の変化に対応したビジョンが十分に描かれているとは言い難い。
(2)齋藤氏の設問──共創によって目指す都市の「価値」とは?
大手デベロッパーの担当者を交えた議論の中で、都市再生におけるエリアマネジメントの役割が明らかになってきた。一方、新型コロナウイルス感染症の拡大が都市の活動に多大な影響を及ぼしている。
「一極集中の課題なども考慮し、改めて東京の価値を再定義する機会とできるはずだ。そもそも、ある時期から、東京の価値や、その価値観に基づいた開発・運営のビジョンは、つくり手の間で共有されずに来てしまったのではないか」と齋藤氏は語る。
例えば、仮にいずれかの地区を金融ビジネスのヘッドクォーターにしたいなら、そのときの価値の指標をどう持つべきか?「グローバルな市場で闘う場合に、各デベロッパーが個別に目標を持つよりも、どんな投資をしてどんな価値を生むのか、指標をそろえて臨んだ方がよいのではないか?」(齋藤氏)

東急経営企画室経営政策グループ 課長の山口堪太郎氏は、「アジア圏であればシンガポールや香港が競合相手になる。ビジネスの担い手が都市を選択するときのインセンティブは何かという話になる。国際的な企業のワーカーが暮らしたくなるようなQOL(生活の質)の観点は欠かせない」と語る。
- 東急の山口氏──「必ずしも生活の場所を固定する必要はなく、QOLに目を向けるなら選択肢は多い方がよい。この議論の場では主に都心の話をしているが、都心における生活と郊外や地方における生活の組み合わせなども考える余地がある。郊外に沿線を持つ東急にとって都心と裏表のテーマとなるものだ」
三菱地所の鈴木氏は、「例えば『幸福度ランキング』はQOLに関する多様な指標を用いている。ただし、個々の指標を向上させる方法は色々と考え得る。そこに街ごとの違いが表れるので、(均質化を避けるには)アプローチの独自性まで評価対象にできるとよい」
- 三菱地所の鈴木氏──「SDGs(持続可能な開発目標)やESG (環境・社会・ガバナンス)なども当然、都市開発のテーマになる。その際に、グローバルな評価基準を意識すべきだ。日本の場合、国内で通用する水準で満足してしまいがちな現実があるが、それでは国際競争力にならない」
都市を評価する指標としては、森記念財団が毎年発表してきた「世界の都市総合力ランキング」(GPCI)がよく知られる。各国の主要都市を、経済、研究・開発、文化・交流、居住、環境、交通・アクセスの6分野で評価し、順位を付ける。
これは「総合力」のランキングのため、各都市に個性を持つエリアの集積が起こっているか否かを知るためには、もう一歩踏み込んだ分析が必要かもしれない。しかし、都市に求められる価値を考える手掛かりとしては貴重な材料となる。
森ビルタウンマネジメント事業室新領域企画部課長の杉山央氏は、「いわゆるビジネスセンターは、オフィス街とは異なる。そこにいるのは生活者なので、いいレストラン、いいエンターテインメントといった多様性が欠かせない」と語る。「東京はGPCIでロンドン、ニューヨークに次ぐ第3位ではあるが、文化・交流という項目が圧倒的に弱い」
- 森ビルの杉山氏──「森ビルは美術館をはじめとする文化・交流の機能にも注力し、六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズでも、23年に完成する虎ノ門・麻布台プロジェクトでも“人を引き付ける”複合エリアづくりを進めている。そうした“都市の磁力”を持つ場所に良い人材が集い、世界に発信できる新しいビジネスが生まれるのではないかと考えている」
noiz共同パートナーで建築家の豊田啓介氏は、そうした都市の価値を固定的にしてしまわずに、「流動的なものとして扱った方がよい」と指摘する。「価値を一義的に定めるような『オンリーワン戦略』によってトップになろうとしても、もはや東京は経済力などの面で難しい立場にあり、すぐに他国に巻き返されてしまう」という理由からだ。
- noizの豊田氏──「価値観が多様化するなかで『世界で一番』と称したとき、そこから疎外される人も多くいる。むしろ価値を固定せず、様々な価値に対するアクセスのしやすさを指向する時代なのではないか。デジタルのレイヤーにおける都市の価値の創出はまだ手探り段階だが、スマート化を前提に流動性を高める戦略を取った方が強い都市になる」
コロナ禍により、集客を前提とする様々なビジネス業態に大きな影響が生じている。しかし、リアルな場所を体験する価値が失われたわけではない。例えば「苦戦はしたが、郊外型のららぽーとなどの商業施設には人が戻ってきている」と三井不動産の雨宮氏は語る。
ネット通販(eコマース)の発展以降、商業空間は滞在体験を重視する「時間消費型」にシフトしてきた。東急の山口氏は、リモートで商品を確かめた後に現物に触れるという順番が、より普通になるとみている。アフターコロナを視野に収め、改めて「都市」の役割を定義する必要が生じている。
- 東急の山口氏──「今まではデジタルでリアルの場所を補完するつもりでいたが、むしろデジタルのUI(ユーザーインターフェース)を基本とし、そこに厳選されたリアルの価値を重ねる考え方に変わらないといけない。それでも街に出たいと感じてもらうために、偶然出会うことのできるような文化的な要素を含め、地域の産業を育てる必要がある」

森ビルの杉山氏は、「人間はコミュニティーのなかで一緒にものをつくったり、認め合ったりしながら喜びを味わう。都市は、そんな生活を促進するための装置だ」と強調する。都市の魅力をデジタルで拡張する試みの1つが、18年に開業した東京・お台場の「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス」だった。
同ミュージアムのプロジェクトに関わった杉山氏は、「『身体を使ってデジタルの空間をさまよう』というテーマを掲げ、実際に訪れなければ得られない体験の提供に力を入れた」と振り返る。19年には230万人が来館し、うち半分が海外からの訪問者だった。「世界を引き付ける『磁力』が生まれたのではないか」と語る。
- 森ビルの杉山氏──「都市開発のDXを進めるという文脈の中で、今後はデジタルのUIが重要になってくる。不動産デベロッパーの立場からは、都市の魅力に関係するコンテンツのUIは、AR(拡張現実)に集約されると想像している。グラス型のデバイスが実用的になれば、都市を訪れたときの楽しみ方が劇的に変わるはずだ」
デベロッパー各社を交えて議論を始めた当初と比較し、都市のスマート化やデジタルツイン化に対する社会の期待度が、より高まっている。エリアマネジメントにおけるIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)、VR(仮想現実)/ARなどの活用は、無視できない要素となってくる。
- 三菱地所の鈴木氏──「コロナ禍を経験した結果、街だけが働く場所ではない、家で働いてもいいし、旅行しながら働いてもいいという考え方が通用しやすくなった。そのため、集合体としての街を飛び越えてサービスをつなげたいという要請が、にわかに強くなっている。そうしたボーダレスな指向性と合わせて都市開発のDXを考えないとならない」
瞬時に状態を切り替えるのが当たり前になった現実を、noizの豊田氏は「離散」という言葉で説明する。「在宅の時間が増えるなかで、70%は会社に貢献しているけれど、おむつも替えるし、食器も洗うし、30%は違う仕事に割り当てるような過ごし方が普通になる。要は居場所や所属もそうだし、あるいは自分の存在自体が離散的な状態になる」
- noizの豊田氏──「人の居場所が流動化するとオフィスのメガプレートの価値が50%になる場合もある。だから30%の居住、10%のホスピタリティといったように、薄くなった価値を重ね合わせ、流動的に用途を編集できるような方向性にしか勝ち目はない。そうした離散的な活動をうまくサポートしてくれるシステムがないところには人が集まらない」
今後、ある目的のために居場所は変えずに“移動 ”したいというニーズが増える。これに対応し、例えばオフィス用途の空間を住居にも学校にも利用可能とし、3分の1に下がりかねない床の価値を1に戻す。「そこまでは簡単なので、隣の街の状況を見ながら、過不足を補い合う連携がシームレスにできるようにする」(豊田氏)という考え方だ。
そうした床の価値の多重化や流動的な使い分けは、ホテルなどを舞台にワークプレイス領域では既に始まっている。これを、より複合的な施設単位や都市単位、国単位で進める時代になる。「価値の創出という意味でも、ビジネスという意味でも、アフターコロナの時代のDX戦略は、そうした流れに従わざるを得ない」と豊田氏は語る。
マネタイズの課題などを抱えているエリアマネジメントに、こうしたデジタル技術によって進展し得る新たな都市サービスを実装できるか。要は、大手デベロッパーの競争と共創によって、「都市開発のDX」がどのように起こり得るか。
(3)齋藤氏の設問──都市開発・運営のDXはどのように起こるのか?
エリアマネジメントは、住民・市民、立地企業、建設・不動産事業者、行政など街に関わる様々なステークホルダー(利害関係者)を横断的に結び付ける役割を果たす。領域が分かれてしまったままではできなかったような新たな価値の創出を担う活動となり得る。
では、そのエリアマネジメントのDX、あるいは都市開発・運営(都市経営)のDXに大手デベロッパーや行政は、どう向き合うのか。デベロッパーとしての不動産ビジネスの中に、あるいは公民連携による都市開発事業の中に、どうデジタル技術を実装するのか。
「見聞する限りでは、“時すでに遅し”と感じさせるくらいに、デジタル技術活用で何を目的とし、何を価値とするかの議論が関係者の間でなされてこなかった」と、齋藤氏は語る。
今、世の中の動きに乗り遅れまいとスマートシティやスーパーシティを手掛けると手を上げた自治体や企業が多い。しかし、「技術的な検討のみに安住している事業体が多いのではないかと懸念している」(齋藤氏)
現実のエリアマネジメントの課題として、不動産オーナーやテナント、行政それぞれの土地・床の管理区分は厳然として存在し、乗り越え難い境界となっている。利用者から見ればサービス提供や情報連携がシームレスになっていない課題は解消できてはいない。

例えば、三井不動産は「グレーター日本橋」、東急は「グレーター渋谷」と呼ぶ広域を対象にエリア再構築のビジョンを展開する。ステークホルダー間の連携には、自社開発地で展開するエリアマネジメントとは異なる難しさがあるはずだ。
以下のように、三井不動産の雨宮氏、東急の山口氏、どちらの言葉にも、マネジメントする対象の広がりに関するジレンマが表れている。
- 三井不動産の雨宮氏──「旧来、土地と住民は切り離せないという前提で行政が機能していた。しかし、住民票がどこにあるかに関わらず、街に関係する人々は全て“住民”なのだと感じている。DXで土地と住民の関係がさらに流動化するなら、行政の財政基盤が崩れていくことになる。そのときにデベロッパーは公共的な役割を補い得るのではないか」
- 東急の山口氏──「国立競技場(新宿区)から中目黒(目黒区)くらいまでの渋谷圏を職住融合の街として発展させようとしている。社内では、『区境』などはあまり関係ないと話している。しかし、いざとなると手続きの面では突然境界線が表れる。民間主導が今後の進め方になるのは間違いないが、前提として行政の支援は極めて大切だと感じている」
「タウンマネジメント」と呼ぶ考え方で自社開発地内を管理・運営してきた森ビルは2021年4月、「ヒルズネットワーク」と呼ぶサービスを発表している。六本木、虎ノ門など各ヒルズを利用する居住者、ワーカー、来街者などを対象にIDとアプリを付与し、各者に最適化した様々なオンラインサービスを提供できる仕組みを整えた。
既に各社は、旗艦エリアではこうした「スマート化」の取り組みに乗り出している、森ビルの杉山氏は、「それぞれのローカルな仕組みが合体し、やがて大きなものに育つ仕組みづくりが必要なのではないか」と語る。
- 森ビルの杉山氏──「これまでは各ヒルズ内だけでみても、居住者やワーカー、買い物に来る人、遊びに来る人が様々な会員カードを使い、それぞれ違うサービスに接してきて状況がある。DXの動きの中で、街をまたいだり移動したりしても一貫したサービスを受けられるよう、事業者が手をつなぎ合う方が都市の在り方としては望ましい」
- 東急の山口氏──「エリアマネジメントには、“公”である行政が担う役割を、”民”が主導して行政が支援する形に組み替えてきた歴史がある。その構図を引き継ぎ、リアルなエリアマネジメントの輪をデジタル領域につなげていける可能性はある。デジタル共通基盤を持つまでにはステップを踏む必要があるので、小さく始める考え方になる」
noizの豊田氏は、00年代、10年代の都心再生の状況からの転換期が来たと強調する。DXの進展や感染症対策の要請から、ボリューム最大化やメガプレート化による効率主義の再開発に限界が表れている。「デジタル技術が可能とする流動化や離散化に目を向けるなら、むしろ逆向きの開発の方がアドバンテージがある」
- noizの豊田氏──「流動化や離散化に対応し、空間や時間を切り分けて価値を生み出すサービスは必然的に、自社開発地の周りのごちゃごちゃした街までカバーできるものとせざるを得ない。土地ベース、床ベースの拡大とは異なる、レトロフィット(既存物)を活用するサービス型に業態転換できるかどうか。非常にポジティブなビジネスの話になり得るはずだ」
エリアマネジメントに要するコストは、エリア広告やエリア内のイベントの収入だけで賄えるものではない。エリアマネジメント団体が存在する場合、その地区の開発事業を主導して大家として関わる大手デベロッパーが、持ち出しで協力してきた現実がある。
- 三井不動産の雨宮氏──「デジタル領域をどうやってフィジカルなエリアに結び付け、マネタイズするか。少し先の話だと考えていたが、コロナ禍で加速し、現実に課題として突き付けられている。自らエリアに貢献しようとする利用者の志向に、我々のDXの動きを重ね合わせたものとなるはずだ。大変なところでもあり、楽しみなところでもある」
エリアマネジメント財源の確保手段としては例えば、地権者から負担金を徴収するBID制度(日本版は18年に法制化)がある。しかし、「境界線を引き、中から集めて中に(サービスを)返すという形のため、拡張性に欠ける面がある」と東急の山口氏は語る。
- 東急の山口氏──「渋谷駅周辺では、公民学の連携でエリアマネジメントの新たなルールづくりを進めているが、ルールの設定がマネタイズに直結しているわけでなない。目下、エリアマネジメントの現場では人的リソースにも原資にも限りがあるため、街づくりとして理想とするシームレスなサービスの提供にまでは至らないのが悩ましい」

今後、都市開発・運営(都市経営)のDXによる合理化や、エリアマネジメント業務における新たなマネタイズ方法の開発が欠かせない。そうした中で、三菱地所の鈴木氏は、デジタル技術の活用による都市の価値の可視化にも期待を寄せる。
- 三菱地所の鈴木氏──「通りに芝生を置いたら訪れる人は増えるか、歩く速度は変化するか。データの取得によってそれらを可視化できれば、社会実験の効果を確認し、次に生かす手掛かりになる。活動の継続性も担保される。そうやってエリアマネジメントの取り組みの価値を証明していければ、投資を呼び込むきっかけになり得るのではないか」
- 三井不動産の雨宮氏──「SDGs(持続可能な開発目標)の観点から、街づくりに対する一定の資金供給は企業として今後も続ける。資金面に関して、私自身は今後、『貢献』『互酬』といった考え方による参加型の発展を期待している。クラウドファンディングのような寄付型や、VRやARと掛け合わせた課金などの併用があり得るはずだ」
自社開発地の周辺も一緒に扱うビジネスとなれば公共性が高まる。行政の取り組みとも親和性がある。そのときに「エリアマネジメントと、そのDXを展開する中で“土地縛り”からの脱却が大切になる」とnoizの豊田氏は語る。「渋谷区から目黒区に入った瞬間にサービスが変わるような在り方は避けたい。そうした不連続が、いまだ至る所にある」
- noizの豊田氏──「土地やモノと情報を、ある程度は分離して流通させることができる状況になっている。しかし、自治体は根本的に土地縛りにならざるを得ないので、境界を越えるサービスはデベロッパーの役割となるはずだ。あるいは渋谷区が目黒区でサービスを提供する状況があり得るのかどうか。刺激的な問い掛けになり得ると考えている」
- 森ビルの杉山氏──「DXに関しては、個人情報の扱いが大きな課題になる。個人のデータを今一番扱っているのはGAFAのような企業で、量とスピードの勝負では勝てない。しかし、彼らにできるのは面的なサービスで、よりローカライズされたきめ細かいサービスには追い付いていない。その部分を補完できるのはデベロッパーなのではないか」
国や東京都からの要請もあるため、都市開発・運営(都市経営)のDXは否が応でも進めざるを得ない。しかし、エリアマネジメントも都市のスマート化も投資対効果が明快ではないため、効率的なリソース配分が前提となる。当初から議論されている1つは、様々な主体がアクセスできるデジタル共通基盤を持ち得るかという命題だ。
(4)齋藤氏の設問──共創のためのデジタル共通基盤を持ち得るか?

都心では、大手各社が隣接するエリアの開発を手掛ける場面が少なくない。パノラマティクスの齋藤氏は、「競争原理を働かせると同時に共創ができれば、東京や日本の魅力を高めるために有効に違いない。各社が得意とするリソースを出し合い、似たような仕組みの部分は共通基盤にしてしまった方が効率が良い」 と改めて問い掛ける。
- パノラマティクスの齋藤氏──「デベロッパーごとに、あるいはエリアごとにデジタル共通基盤を持つというよりも、みんなでシェアした方が理にかなっている。各エリアに文化の集積や金融機能の集積を図るというときに、いったん民間みんなで基盤を共有し、そのうえで各社が独自性のあるものを展開するという考え方は成り立たないのか?」
大丸有(大手町・丸の内・有楽町)エリアにおけるスマートシティーの取り組みは、国土交通省の先行モデル事業として進む1つだ。主導する三菱地所の鈴木氏は、エリアマネジメントもデジタル技術も「横断力」がカギである点に着目している。
- 三菱地所の鈴木氏──「都市は元々、オールジャンルで体験やサービスを提供する場である。それらを横断的に扱うのがエリアマネジメントの特徴だ。一方、デジタルにも、色々な体験やサービスをシームレスにつないだり総合化したりする働きがある。エリアマネジメントとデジタルを掛け合わせたインフラ整備をどう推し進めるかが課題ではないか」
参考になる前例として、三菱地所の鈴木氏は米ニューヨーク市におけるオープンデータ化の取り組みを挙げる。例えば公共空間の活用に関し、電子化で申請が楽になる他、申請状況がマップ上に可視化されるので「行政内を含めて横の連携を進めやすくなる。共通基盤の在り方のヒントになるはずだ」
- 三菱地所の鈴木氏──「他社間との共通基盤に関しては、連携してアクティビティーを生み出す仕掛けは“民”が担い得る。ただし、その活動を支える共通のルールづくりには行政の協力が不可欠だ。ハードの改変を含むロードマップを持ち、官民それぞれが考えていく必要がある。人流など分かりやすいデータ活用に、まず着手するのが大事ではないか」
デジタル技術によって、様々な指標を定量的に分析できる時代になった。パノラマティクスの齋藤氏は、「デベロッパーが協力し合ってエリアの価値を測る仕組みを開発してもいいはずだ」と語る。「日本企業は効果実証がとても下手で、都市開発でも投資対効果の事後的な評価はしていないに等しい。感覚論に流されているきらいがある」
- パノラマティクスの齋藤氏──「日本企業の場合、効果測定を嫌がってPDCAがPDCで止まる。2周目に入らず、別の1周をつくってしまう。そうではなく、評価・分析をしながらクイックに街の姿を変えていけるサイクルを生む必要がある。その際、KPI(重要業績評価指標)ではなく、KGI(重要目標達成指標)が大切であるのを忘れてはいけない」
東急の山口氏は、「都市データをセンシングする試みは、どんどん進めた方が良い。ただし、ある施策の成果を街全体で評価・分析するとなると、影響要因が複雑すぎて難しい」とみる。施策そのものの是非を問うよりも、「次なる都市政策の意志決定要素として使うのが適切かもしれない」と語る。

また、noizの豊田氏は、「データを取るのは当然として、評価・分析するロジックを開発するR&D機能が日本には全く足りていない」と語る。「例えば、解析のためのAIエンジンをどのようなものにするのか、データをどのようにかませるのか。投資環境も開発環境も遅れているという課題がある」
三井不動産の雨宮氏や東急の山口氏は、デジタル共通基盤を築くには、行政の力に頼らざるを得ないとみる。しかし、齋藤氏は、主従関係は変えてしまい、「民間から立ち上げたものを最終的に行政がルール化するぐらいでないと立ち行かないのではないか」と語る。これには豊田氏も賛同する。閉じた地区に立脚するエリアマネジメントの個別のスケールではマネタイズが難しい。「開かれたサンドボックス(実証実験場)を設け、会社、業界、都市全体が明らかに潤うという連携スキームを可視化しないと展望が開けない。デベロッパーには、そうしたサンドボックス用地を持つという圧倒的な強みがあるはずだ」
豊田氏は、大阪商工会議所が大阪市北区に開設した「コモングラウンド・リビングラボ」をディレクションしている。スマートシティー開発やスマートビル開発の進展に不可欠となる諸技術を様々な企業・団体が共同で実験する場となる。フィジカル空間とデジタル空間を融合させるSociety 5.0の実現を民間主導で試行錯誤する取り組みとなる。
- noizの豊田氏──「様々なサービサーやメーカーが集まり、お互いを“モルモット”とするような実験を繰り返しながら全体最適化の流れを導き出す。新たな都市サービスのために、どんな情報レイヤーを重ね合わせるのか、どんな投資が必要なのかを見極めていかないとならない。まず、どこかにリアルな場所が提供されなければ話は始まらない」
森ビルの杉山氏は、これからは事業用や実験用の床(場所)を貸すだけにとどまらず、「都市の魅力を高めるためのコンテンツや、場合によっては新たなサービスを、デベロッパーがリスクを取ってつくり出していく必要がある」と主張する。その際のキーワードとして「体験価値」を挙げる。
- 森ビルの杉山氏──「これまでは駅からの距離など不動産スペックで賃料が決まっていた。むしろ、どんな人がいるのか、どんなコミュニケーションが生まれるのかといった体験価値を重視すべきだ。他人任せにせず、人々の交流、商流、物流などのサービスインフラづくりにも大家であるデベロッパーが乗り出す必要がある。それが街の個性になる」
これまで1回約2時間のセッションの中で、大手デベロッパー各社から多角的な視点が持ち込まれてきた。回を重ねて議論を深める中で、現場の担当者の間では、事業者間の共創に対する期待があることが分かってきた。
2021年、齋藤氏の発案により、都市開発のビジョンを巡る議論の段階から踏み出し、何らかの「アクション」に結び付く作業を各社からの参加者と共に進めてみることになった。今後の展開に期待したい。
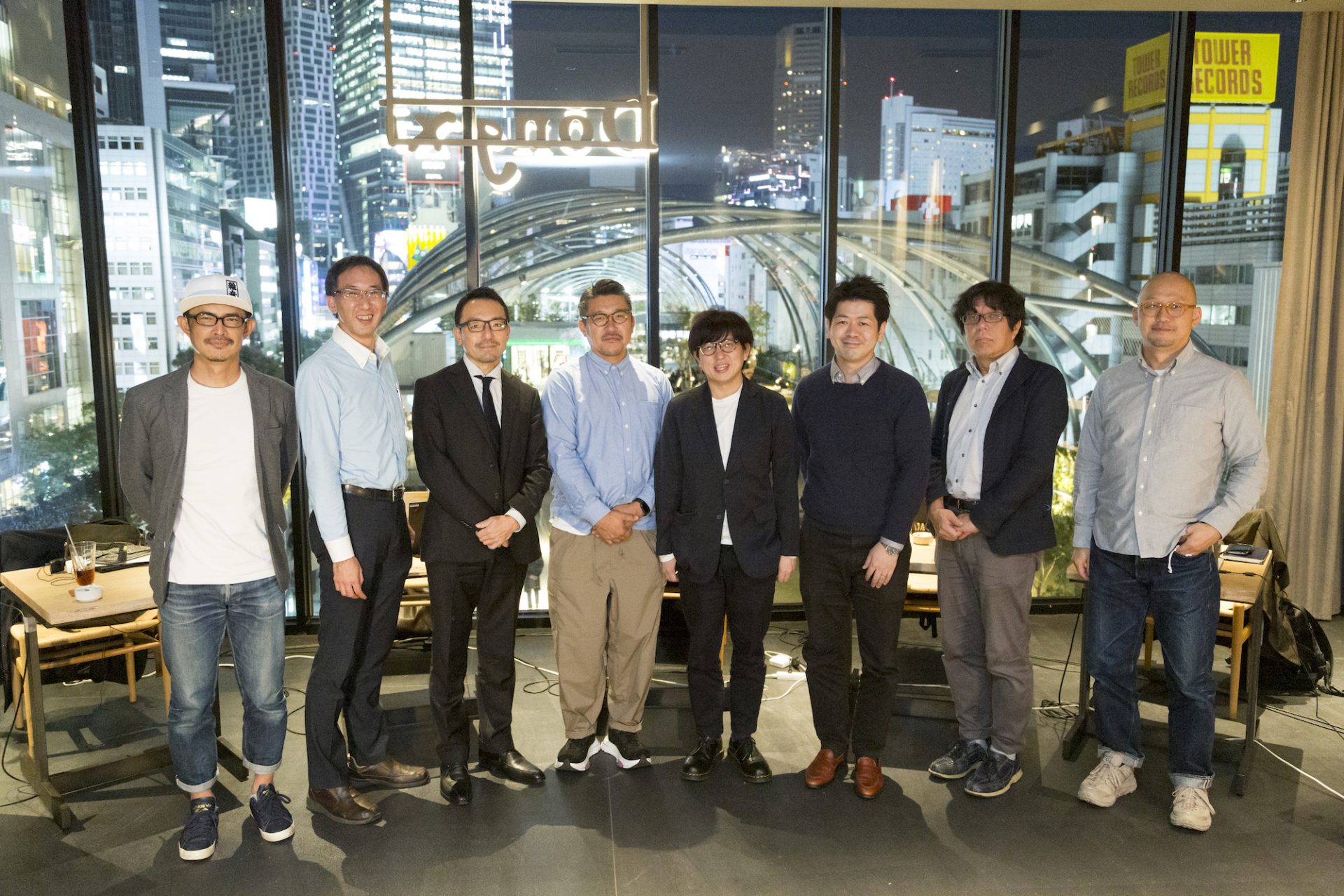
Photo : Chihoko Ishii
