都市開発事業と運営・エリアマネジメント
ライゾマティクス齋藤氏より、都市開発における先導的なマスタープラン不足の現状について課題の投げ込みがなされた初回議論から 初回議論を受けて開催されたvol.2「都市開発におけるコンセプトを俯瞰する」での議論を経て、202X時代の幕開けとなる今回は「都市開発事業と運営・エリアマネジメント」をテーマに開催しました。今回は丸の内・大手町エリアの交流拠点「3×3Lab Future」へと会場を移し、都市開発事業者それぞれのエリアマネジメントの取り組みを伺うとともに、これからどのように街と関わりながら運営することができるか、互いの意見を交わし合いました。
▼今回登壇者
齋藤精一氏(ライゾマティクス・アーキテクチャー主宰)
豊田啓介氏(noiz共同主宰/gluon共同主宰):今回は進行役
山本恵久氏(日経xTECH・日経アーキテクチュア編集委員)
田中陽明氏(春蒔プロジェクト株式会社 代表取締役/co-lab企画運営代表)
—
中 裕樹氏(森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 パークマネジメント推進部兼TMマーケティング・コミュニケーション部)
藤井宏章氏(三菱地所株式会社 開発推進部理事 エリアマネジメント推進室長/NPO法人大丸有エリアマネジメント協会事務局長/DMO東京丸の内事務局長)
雨宮克也氏(三井不動産株式会社 開発企画部 開発企画グループ長兼環境創造グループ長)
山口堪太郎氏(東急株式会社 都市経営戦略室 戦略企画グループ 企画担当 課長)
ー前回振り返りと今回テーマー
「202X URBAN VISIONARY」の発起人である齋藤精一氏は、これまでの経緯を振り返るとともに、今回の趣旨を説明しました。東京をはじめとして大規模な開発事業がこれまでにない勢いで進むなかで、個別の最適解を求めていると街が「金太郎飴」のような姿になるのではないか。少子高齢化やグローバル化が進み問題が山積する時代にあっても、街が既存の枠組みと開発メニューのなかでつくり続けられて大丈夫だろうか。こうした問題意識と危機感に対して、再開発を進める立場のさまざまな事業者が集まり、オープンに話し合うことが必要ではないかと「202X URBAN VISIONARY」は始まりました。
先回の第2回目では、街づくりの話とともにエリアマネジメントの話題が上がり、各事業者の知見やノウハウを共有する機会を持つことの重要性が議論されました。そこで第3回目は、エリアマネジメントをメインのトピックとすることに。豊田啓介氏を司会進行役として、各事業者の取り組みをみつつ、共有すべき視点や課題点を深めていくことが狙いとされました。
豊田氏は、2020年に入ってトヨタ自動車がスマートシティ構想を発表したことを挙げながら、今エリアマネジメントを取り上げる意義を指摘しました。「エリアマネジメントをデベロッパーが取り組んでいる動きは、建物をつくってきた各社が、モノを売るのではなくコトを売るようになってきた文脈でも捉えられます。また、あえてヒューマンスケールでユーザー視点でのエリアマネジメントの視点に戻ってくるということかもしれません。今回は、エリアマネジメントを各社が差異化の要素として、もしくは横のつながりや産業全体の価値の増幅のためにどう利用されているかを引き出したいと思っています」。続けてライトニングトークとして、登壇者が自社のエリアマネジメントの取り組みを短く紹介しました。

ー事業者ごとのエリアマネジメントの取り組みー
雨宮克也氏は、三井不動産は都心部では日本橋、東京ミッドタウンそして東京ミッドタウン日比谷などでエリアマネジメントを展開しており、その目的のひとつが「地域の価値と企業価値のウィン・ウィンな関係」にあることに言及。日本橋では、直近で「日本橋再生計画第3ステージ」を発表、その街づくりの考え方は「共感・共創・共発」であるとして、「モノからコト」への移行を意識していることを説明しました。首都高速の地下化に合わせた親水空間の創造、産業創造の取組み、国際的なイベントの開催などの構想を挙げ、エリア内外のネットワークに重点を置いて構想中であることを紹介しました。
中 裕樹氏は、森ビルが取り組んできた、都市のグランド・デザインのなかで「街の鮮度を保つ」活動としての「タウンマネジメント」を紹介。一例として、六本木ヒルズでは、森ビルが統一管理者として街のブランディングと同時に街をメディア化してマネタイズし、そこで得た収益をさらにブランディングに投下するという仕組みを説明しました。また今後は、六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズで培ってきたアートや緑化による都市の高付加価値化のノウハウを、虎ノ門・麻布台プロジェクトなど新しい事業に応用させていくと語りました。
藤井宏章氏は、三菱地所の大丸有の地区で「エリアマネジメント」と言う概念のもと、「街全体の価値を上げる」ことを目指した街づくりを長年してきた経緯を紹介。民間の地権者と行政が一体となった「まちづくり懇談会」でビジョンを共有し、共通認識のもとに実現するためのルールや手法が決められていることを大きな特徴として挙げました。またNPO法人の大丸有エリアマネジメント協会が域内の公的空間活用の担い手となりイベントなどを実行していること、一般社団法人エコッツェリア協会が今回の会場となった「3×3 Lab Future」を運営し、そこにさまざまな人が集うなかで、社会課題を探るアンテナ役として、次の街づくりのテーマを拾えるようにしていると紹介しました。

山口堪太郎氏は、渋谷再開発の経緯から、渋谷駅前エリアマネジメントの取り組みを紹介。Vol.2でも紹介した「生活文化の発信拠点」というまちの指針から「遊び心で、渋谷を動かせ。」というコンセプトを導き、多様な担い手との協働を標榜。①国・都・区・事業者の協議会を通じて新しいルールづくりを行い、②事業者中心の社団法人が、新しいルールに基づき、公共空間から広告収益を得て、③その収益を、サインの統一やWi-Fiスポット、場づくり等、街への再投資してきた一連の流れを紹介しました。ポイントは、「渋谷らしさ」を大切にしながら、民主導を官が支える「新しい公共」を作り続けていくこと、としました。
ーエリアマネジメントにおける「クリエイター」ー
各事業者の取り組みについての説明を受けて、「202X URBAN VISIONARY」ファシリテーターの田中陽明氏は、エリアマネジメントに対するクリエイターの役割を指摘しました。「デベロッパーは、建物に入居する街の人のことを“プレイヤー”と呼ぶことがありますが、場を提供する側と利用する側という線引きを感じることがあります。でも登壇者のように事業者の個人個人もつくりたい街を描いておられて、皆さんがクリエイターなのだと思います。それぞれが自分たちの想いで街をつくろうとするなら、街の個性は生まれるのではないでしょうか」。田中氏はまた、自身が運営しているco-labに入居するクリエイターが、渋谷CASTの広場での企画提案を行ってイベントを手掛けた事例を紹介。開発の企画段階からも、クリエイターの意見が反映されることの有効性と可能性を示唆しました。そして「3×3 Lab Future」のようなコワーキングスペースが、エリアマネジメントのエンジンのような場になりつつあることを指摘しました。
齋藤氏は自身が「クロスセクター」と呼んでいる現象、つまり企業が業界のボーダーを超えて活動することが当たり前となっているなかで、デベロッパーも建物をつくり管理するだけでなく、街のホスピタリティやブランド価値を真剣に考えるフェーズにあることを指摘。ICT化やIoT、AIが進み新たなシステムが構築される際に、人間中心の思想であるべきではないかとの考えを示しました。またニューヨークのブライアント・パーク、ハイライン、シェッドなどを実現したBIDやドネーションといった仕組みを日本ではなぜできないのか、という疑問を提示。「日本ですべき、もしくは日本だからこそできるエリアマネジメントは何なのか。将来に向けてどう連携していくべきか、棲み分けていくのかと、オプティミスティックな議論になればいいと思います」と期待を高めました。

ー「エリアマネジメント」を定義するー
豊田氏は、幅広く用いられる「エリアマネジメント」の定義をこの場で共有することを提案し、まず雨宮氏に説明を求めます。雨宮氏は「エリアマネジメントは和製英語であり、その起源は大丸有地区にみるように積極的な都市開発による都市機能更新がもたらすエリア価値の向上、つまり「作る」から「育てる」、にありました。しかし最近ではその「育てる」部分がさらに進化して、多様な人々が集いそこから産業や文化の創造が起きることを企図する活動となってきています。あえて議論のために言うならば、第1期のエリマネが「囲い込み」だとすれば、第2期ともいうべき今は、「放牧」のようなイメージです。多彩な分野や個性により起きるイノベーションを導くために場を作り、牛飼いの目で全体をマネジメントすることがデベロッパーに求められていると感じます」と指摘しました。これは2008年の「エリアマネジメント推進マニュアル」以降、「新しい公」や復興まちづくり、SNS等を通じたコミュニケーションの多様化とまちづくりにおけるクリエーターの役割の進展など、エリアマネジメントの仕組みが都市部のみならず広く展開されていった時期と重なると概説しました。
藤井氏は、大丸有エリアマネジメント協会が2002年に発足して以来、10年ほどは地道な活動だったと振り返ります。「一気に加速したのは、この3〜4年のことと思います。1つの要因はそれまでの地道な活動の積み上げのもとにさまざまな規制緩和が進んだ結果、道路などが具体的に使えるようになったこと」と指摘しました。民間ではイベントホールや広場が使える一方で、エリアマネジメント団体では活動する場がなかった背景を説明しました。また「オフィスビルがコモディティ化し、利用者はビル自体の商品性だけではなく、そこに行くと新しい機会がある、会いたい人に会えるなど、別の価値を求めるようになっています。デベロッパー側も、街をどのようにつくっていくかに重点を置くようになりました」とも言及。そして社会課題が細分化し表面化するなかで、エネルギーコントロールの課題やイノベーション創発など、ビル単位でなく街としての環境づくりが求められるようになり、いわゆるソフト面や仕組みづくりの観点でエリアマネジメントに対する期待が高まったと指摘しました。
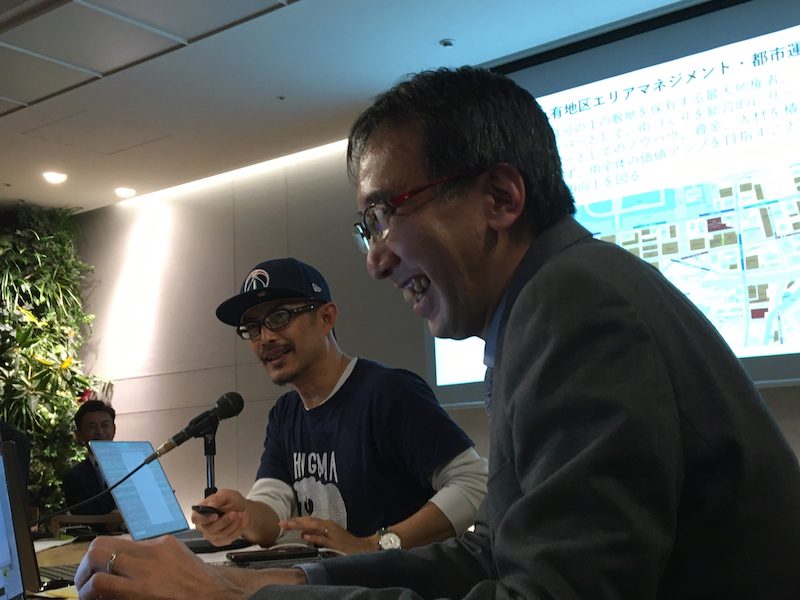
山口氏は、エリアマネジメントという言葉自体の捉えられ方に幅があること、フリーライダーが忌避されることに触れた上で、駐車場ルールなどを例に挙げ、「まちで一番大事な「公」の空間を「共」に開放し、まちを使うひとみなに対する価値を提供するのだから、実績を重ねて自然と範囲が拡がるのがよい。」と語ります。それに対して齋藤氏は、エリアの中で異なるステークホルダーが集まるときに、デベロッパー間が協力してエリアのブランドをつくっていこうという活動自体が始まっているかを質問。雨宮氏は、渋谷区の公園と商業施設の再開発事業を例にして、「デベロッパー同士では普段から様々な事業や業界活動等を通じて人的ネットワークがあります。しかしそのもう1つ手前には自治体はもちろん住民あるいは各種の地元組織があり、きちんとプロセスを踏んでいくことによりそこが協力の場としてのプラットフォームとなっていただけると考えています。また、これから実際に施設のオペレーションが始まるとまち全体で調整が必要なことがでてくることが考えられます。そのような事態に対応するために、さまざまな工夫によりデベロッパー間でもコラボレーションができるのではないでしょうか」と予想しました。山口氏も「デベロッパーでも、エリアマネジメントの担い手同士の連携はより密です。実際に5年ほど前、渋谷で社団を立ち上げる際には大丸有はじめ多くのまちの方にたくさん教えていただきましたし、その後、渋谷で解けたことは、恩返しのつもりで次のまちの方にこころよく共有しています。」と例示を挙げながら補足しました。
ーマクロな視点でエリアの役割をもたせるー
齋藤氏は、同じエリア内でデベロッパー間の競争をしている時間的な余裕はなく、マクロな視点でエリアの役割をもたせることを主張しています。「マクロで見たときのエリアマネジメントは、商店会など地元の方々とも一緒にブランドをつくる必要があるでしょう」として、中氏に森ビルの虎ノ門・麻布台のような大きなプロジェクトでは、エリアマネジメントとしてどのようなフェーズにあるのかを質問しました。中氏はパークマネジメント推進部という新設の部署で、広場の活用の方法や街と連動させることに取り組んでいることに触れ、「周辺にある駅の鉄道事業者や病院と連携し、また行政とも帰宅困難者の受け入れなどをどのようにするか、周りのデベロッパーも含めて大きな協議会をつくり、このエリアの在り方を議論しながら進めています」と、賑わい創出は無論、「安全・安心」や「緑」といった視点でも広範囲に連携していることを述べました。

豊田氏はそれを受けて「エリアが大きく複合的になると、地域の課題として捉えられていたものが、むしろプレイヤー間でだんだん価値創造になっていく」ことを推察します。一方で、エリアマネジメントでは単体で利益を生まないことを指摘。「不動産の賃料収入とは違うかたちになっていくとき、マネタイズやビジネスモデルはどのように捉えられているのでしょうか?」と質問を投げかけました。
雨宮氏は「常に問われる課題」とし、その理由について因果関係を証明しづらいことを挙げます。「欧米の受益者負担によりエリアマネジメント活動を行うBIDも、詳細な因果関係を証明できているとは言えません。それでもアニュアルレポートの中で、通行量がこれだけ増えた、売上がこれだけ増えた、ゴミをどれほど回収した、という成果を整理して説明します。エリアマネジメントでもその効果を伝える努力は必要だと思います」。山口氏は「中小物件のオーナーを含め範囲内の全員から固定資産税に上乗せ徴収し、数年で指標が悪ければ即解散、という欧米的なBIDをそのまま導入しても実現味は薄い。」とした上で、「BID的な資産価値の話も、例えばツーリズムなど、何がよくなればまち全体がよくなるのか、から具体に逆算した複数の指標と組み合わせて、まちを俯瞰して見続けるサイクルを回さねばならないのではないでしょうか」と意見します。雨宮氏も、「エリアに貢献することでエリアから受益する、という理念にもとづいていると言わざるを得ません」と同意しました。「ただ、地域再生エリアマネジメント負担金制度ができて受益の範囲内でエリアマネジメントに要する費用を負担するという制度設計がいよいよ実装されます。すでに多くの学識者や実務者が取組んでいますが、受益と負担の関係を定量的に分析する手法の開発が今後進むことが期待されます」と予想しました。
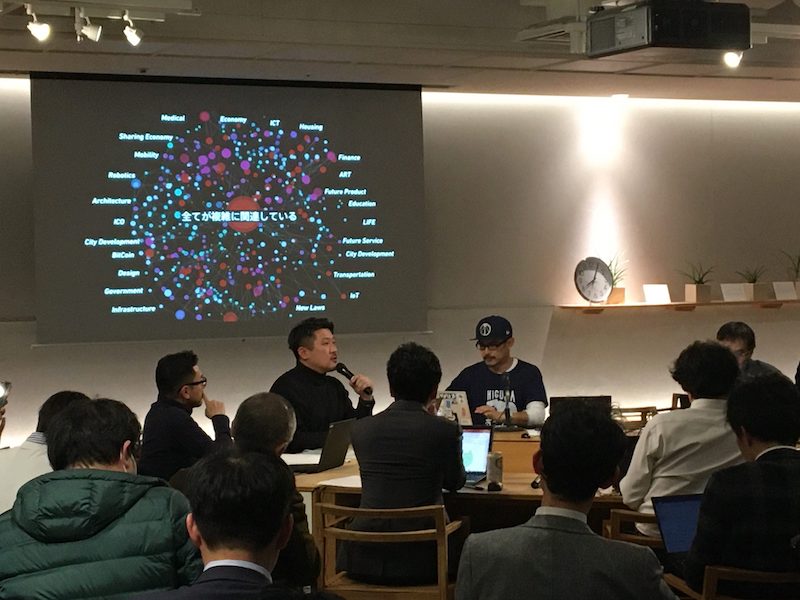
ーエリア価値をデジタルで測るー
齋藤氏はここで「ICT化によって、利益率を定量的に数値化しアナライズする時代が来たと思う」と指摘。デベロッパーが協力して、エリアの価値をデジタルで測る仕組みを開発することを提案しました。「数値化によって意図せず明るみに出てしまうことがあるかもしれませんが、恐れてブレーキがかかっていると何も前に進みません。日本でドネーションがなかなかないというのも、価値をダイレクトに分かろうとしない風潮があるためでしょう。日本は効果測定がとても下手で、例えば1兆円を投資しても、その後の効果測定はしていないに等しく、感覚論に流されてしまいます。それでも判断基準をしっかりとする必要があり、来た人が多いというだけでなく、エモーションに刺さっているのかはインタビューも含めて測らなくてはいけません」と言及しました。豊田氏はそれを受けて「データを取るところから始めるのは当然のこととして、分析するロジックを開発するR&D機能がまったく足りていないように思います。例えば、AIで解析するためのエンジンをどのようなものにして、どのようなデータをかませてどう調整していくのかというようなことには膨大な投資が必要ですが、そうしたプレイヤーが日本にはいない気がします」と答えました。
齋藤氏は「ゑびや大食堂」という店でカメラを設置してデータを取り始め、未来予測や店舗分析サービスの「EBILAB(エビラボ)」につながった例を示し、「ライトにできることは皆さんでまずやってみて、広域でマクロに連携する方向もある気がします」と後押ししました。山口氏も「多様な担い手に参画いただき、都市データをセンシングし続け、指標化することはどんどんやっていくべき。しかし、まち全体に効くような施策の成果要因は多様すぎ、施策そのものの是非よりも、トライアンドエラーとして次なる都市政策の意志決定要素として使えるとよい。」と答えました。

豊田氏はこの点で中氏に、自社の一体開発で複合施設を持っている森ビルに可能性が高いとみて、戦略があるかを尋ねました。中氏は、「BIDのように賃料からマネジメントのためのコストを支払い、質の高いサービスを提供する仕組みはあると思いますが、BIDの導入で集う人のライフスタイルはそれほど変わらないのではないかと感じています。虎ノ門・麻布台プロジェクトは、人の営みから考え『モダン・アーバン・ビレッジ』という街のコンセプトを掲げているのですが、ここに来ると何かが違う、例えばゴミの捨て方が違うといった人の営みが変わる仕組みを取り入れるとします。その裏側に実はテクノロジーがあるということができるといいなと考えています。入り口がテクノロジーや集金の仕方ではビジネスライクで堅苦しくなるので、そこにクリエイティブという力を入れたい。社外のアイディアも広く聴きながら、イベントだけでなく、新たな視点を取り入れて行きたいです。そして、既存の施設ではデータの分析が難しい側面もあるので、新しいところで初めからデータ分析を志向し、そのためのシステムを組み込みながら、街を設計するのがいいのではないかと考えています」と感想を交えて答えました。
ー社会や産業構造の変化に迅速対応できるまちづくりー
山本恵久氏は、先回までの議論の中で開発がマスタープラン型からプロセス型へ移行する話題がたびたび上がってきたことを踏まえ、測定が街のつくられ方に機敏に影響を与えることがあるのかどうかを尋ねました。この質問を受けて齋藤氏は、再び日本の傾向を指摘。
「日本はPDCAが回らない国だと思っていまして、効果測定を嫌がるのでPDCあたりで止まるのですね。2周目に入らず、次の新しい1周をつくってしまう。そうではなく、すぐにレスポンスできるような街の姿を描くことは必要でしょう。防災や災害時の対策、経済情勢が変わったときにプログラムを一気に変えられるような街です。例えば、賃料の坪単価を3万8000円であったところが、状況が変わったときにクイックに2万4000円という指針ができるようなプランも、エリアマネジメントやデータドリブンの方法です。そうした実践はあるのでしょうか」と投げかけました。

これに対して直接的には答えが出にくいなかで、雨宮氏は日本橋での取り組みを紹介します。「日本橋では『ライフサイエンス』という新しい領域を掲げてオフィスの使われ方や知のイノベーション、すなわち産業創造の場が変化していることをとらえたビジネスモデルに取組んでいます。もともと日本橋は薬問屋の街で今でも地元企業に製薬会社さんが多くあります。いわゆる「ドライラボ」と言われる事務打合せのためのスペースを用意したことが始まりです。しかしビジネスの現場では「ウェットラボ」という実験スペースが必要であったり、短期間でチームアップして研究開発するためのスペースが必要であったりと新たなニーズが見えてきました。この日本橋の例からもわかるように、様々な分野でビジネスモデルはオープンイノベーション型へと変化しており、多様な分野の多彩な人材が街に出入りすることになりそこに様々な才能の化学反応が起きています。エリアマネジメントの中でこうした場と情報を提供していくことで、東京の中での地域性、差異化ができるのではないかと思っています」。
山口氏は「渋谷はクリエイティブコンテンツ産業。前回まででも触れたが、街ごとに個性を、が原則。」と触れた上で、「しかし共通するものもある。よく『イノベーション」とよく言わるが、都市では『オープン・イノベーション』でなければ意味がない。発露してコトを起こすまでの間にクリエイターが混じってジャンプするような過程が必要で、まちそれぞれの産業の個性に沿った、多様な交流創発機能は全てのまちにあるべきではないでしょうか。」と指摘しました。続けて藤井氏は、大手町を抱く大丸有が、世界に向けた場として「FINOLAB(フィノラボ)」を設けて好評を博していることを紹介。「FINOLABにはイギリスなどのフィンテックカンパニーや日本の大手銀行が拠点を置き、一緒に議論したり新しいサービスの開発をしています。そうした活動を後押しするエリアマネジメントの新たな活動として、都心型エリアMICE誘致・創出を目的とした『DMO東京 丸の内』を立ち上げ、例えば毎年開催される「FIN/SUM(フィンサム)」といったイベントなどの開催支援をしています。オールインワン型の大きな施設の中だけでMICEを完結させるのではなく、街として、面として国内外から人を迎えMICEイベントを楽しんでもらうという姿を目指しています」。

齋藤氏は複数の取り組みの話を受けて、「やはりモノをつくり表現するクリエイティブな人がエリアマネジメントの中では大事ですし、エリアマネジメントが1つになるためにはイベントなどを開催することで始まることも多い」としつつ、雨宮氏の言及した「ドライラボからウェットラボに」という内容に注目。「本当のウェットラボになると用途地域にも関わってくると思うのですが、インキュベーションやエリア自体が成長することを考えると、用途地域の違うものを隣につくりアップデートできるようになるといい」と、インセンティブのかたちも、容積率の緩和とボーナス以外にさまざまあるのではないかと指摘しました。
ーこれからのインセンティブの形ー
豊田氏は、登壇者にインセンティブの希望を募ります。山口氏は「まずオーソドックスには補助金、税、容積とあり、時流や制度に依存する補助金よりも本来は税で、それを原資に公益還元できればよいが一番難しい。となると民主体で動ける容積の工夫、例えば、もう少し広域に捉え、木密解消と緊急整備地域の異なる社会課題容積交換のような提案をしたことがある。」と語りました。中氏は「再開発で道路をつくらなければならないとき、『道路』と規定せずに、もっと柔軟に、交通インフラの機能を担保すれば、その在り方の選択肢は幅広く設ける、というインセンティブがほしいですね」と語りました。田中氏は「渋谷CASTではクリエイターに入ってもらって公開空地でのイベントを企画して開催してきました。中間的で自由な使い方の要望がルール化されていけば、本当に使いたい方法が定着してくのではないでしょうか」と意見しました。雨宮氏は、「都市が速いスピードで変化するなかで、土地利用のかたちが変わり、用途地域の画一的な設定が足かせになっていると感じます」とし、「乱開発は避けつつも、さまざまな状況に対して用途地域も柔軟に見直す仕組みが必要と思います」と要望を口にしました。

これらの意見を受けて豊田氏は「社会のインフラをデベロッパーがつくるという意味では、民間と行政の境界がどんどん曖昧になり、行政的なことを民間がやる、一方で民間的なことを行政が行う仕組みがシームレスになっていくでしょう」と予測。藤井氏は「インセンティブというのもそうですが、都市計画上の用途の見直しが必要と感じます。これから例えば住宅なのかオフィスなのか分からないようなものはたくさん出てきますし、それらに対応できるように変えてほしい。また、民が主体で進めるエリアマネジメントは官に代わってその街を良くするという半公共的側面を持っており、固定資産税や都市計画税の一部を振り分けられるなどの仕組みがあるといいのではないかと思います」と指摘しました。
ー会場からの質問ー
時間が差し迫ったところで、会場からの質問を受け付けました。ここで出たのは「各企業が過去のプロジェクトでためてきた知見を、リソースとして外に開示するのか自社内で掘り起こすような取り組みはあるのか」という質問です。それに対して各登壇者が顔を見合わせるなかで、山本氏は「建築の分野では重鎮に聞くような文化は多くあると思うのですが、都市分野では確かに蓄積がよく見えてきません」と指摘しました。齋藤氏は「オーラル・ヒストリーには、言語化されて共有される文化的な強さがある」と強調。高度経済成長期の方向を決めた方々がいなくなりはじめ、大規模な再開発に関わられた方々が現役を引退される今の時期に、事実とノウハウを伝えるべきではないかと意見を述べました。

ー最後にー
最後にまとめとして、齋藤氏はこの日の議論から受けた気づきを話しました。「思っていたよりも互いが連携しそうだなと感じました。エリアマネジメントは、そのエリアの価値を高めることから始まっていたものの、今は『価値をつくる』ことに役割が変わりつつあるように思います。そのときに、エリアマネジメントでも皆さんが力をかけておられることが今日の話でも分かったので、会社仕切りではなくエリア仕切りで、スクラムを組んでエリアのブランド価値を上げていくことが大事ではないでしょうか。そしてインセンティブの話では、特例措置のようなことは国や行政でしかできないので、エリアマネジメントが価値を生むことをもっと理解いただかないといけないでしょう」。豊田氏は「エリアマネジメントが1.0から2.0の時代に入ったと強引に話をすると、これまでのエリアマネジメントのイメージよりももう少し戦略的なテナントマネジメント、もしくは医療系やフィンテック系など、ディレクションのマネジメントもシームレスにつながっているように思います。同時にアートも、彫刻のような物質的な作品の次に、アート的なイベントやコンテンツに代わられつつあるとすると、モノからシステム的なものに移行する流れがあるでしょう。今日の話ではエリアマネジメント的な内容とコンテンツデザイン、全体のブランディングがつながる印象がありました」と振り返りました。そして再開発からその周辺、都市全体とスケールを横断するビジョンにエリアマネジメントが拡張的につながる可能性について、またエリアごとに差異化をしたうえでどのように共存して可能性を広げるかについては、今後も継続的に議論していきたいとしました。
3回目の議論を終え、さらに話題の広がりと気づきを得た「202X URBAN VISIONARY」。次回のvol.4でも、いっそう深い議論が繰り広げられることに期待が高まります。
ーspecial thanks to 『3×3Lab Future』ー
今回会場として利用させていただいた3×3Lab Future。丸の内と大手町エリアのビジネス交流拠点として、「交流・啓発機能」「ラボラトリー機能」「ショーケース機能」の3つの機能をベースに11のゾーンからフロアが成り立ちます。
本編トークが進む舞台裏、ワークショップキッチンでは懇親会用のフードの準備が進められました。「急げー!」「間に合うかな!?」などと声を掛合いながら大慌てで調理が進み、ぴったり時間内に出来上がったお料理は写真に入りきらない程の品数!この日のために仕入れられた新鮮な野菜やお米を使ったメニューはどれも家では食べられないけど、家庭的な安心する美味しさでした。豪華な食事を囲みながら、懇親会パートがさらに盛り上がったことは言うまでもありません。ライゾマ齋藤氏からは「こんなに誰も最後まで帰らない懇親会は初めてです!(笑)」という最後の挨拶に会場は笑いに包まれました。



